 豊玉姫
豊玉姫 和風諡号の意味
諡号諡号、あるいは諡は、主に帝王・相国などの貴人の死後に奉る、生前の事績への評価に基づく名のことである。「諡」の訓読み「おくりな」は「贈り名」を意味する。漢風諡号鎌倉時代に成立した『日本書記』の注釈書『釈日本記』に引用された元慶~承平年間の...
 豊玉姫
豊玉姫  継体天皇
継体天皇 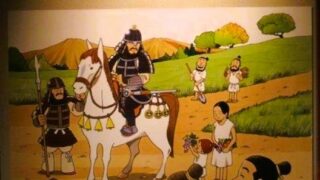 継体天皇
継体天皇  天日鉾
天日鉾  継体天皇
継体天皇  聖徳太子
聖徳太子  福岡県
福岡県  豊玉姫
豊玉姫  大分県
大分県  大分県
大分県